
新魔王j’s2000
復活して10号目のホットバージョンである。この号では、先に予告していた、New86の心臓にレガシーの3リッターエンジンを移植したマシンのインプレッションが披露されるものと期待していた。それが、最後まで出てこない。
早速、本田俊也編集長に抗議の連絡を入れてしまった。
「そうなんです。この号は、魔王決定戦と、新しいレーシングドリフトのガチンコ団体戦なんですが、その2本の密度をあげたら、尺がなくなって……。次の4月売りで12月に筑波で収録したハチロク・バトルと一緒に紹介しますから。それで、出来はどうでしょう?」
「いや、ざっと流して観ただけだから。これからジックリと……」
「よろしくお願いします」電話を切ったあと、大きな体の割に、いつもひかえめな本田編集長の声に、これまでにない力がみなぎっていたのに気付いた。この号の献立と料理の味に相当な自信があるらしい。では改めてVol.120を、じっくりと賞味してみようか。
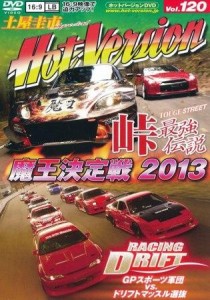 舞台は落葉が路面のあちこちに吹きたまった群馬サイクルセンター。「峠最強伝説 魔王決定戦2013」のオープニング。まず3人のレギュラーたちの賑やかなおしゃべりからはじまった。
舞台は落葉が路面のあちこちに吹きたまった群馬サイクルセンター。「峠最強伝説 魔王決定戦2013」のオープニング。まず3人のレギュラーたちの賑やかなおしゃべりからはじまった。
織戸学が露払いをする。
「さぁ、はじまりましたホットバージョン120。120号ですよ、土屋さん」
土屋圭市が「ご老公」よろしく登場して、読者(ベスモ以来の呼び方を継承してくれている)へ感謝の言葉をおくる。つづいて谷口信輝が上手に締めたところで、ゲストたちにカメラが移っていくという定番。今回はさらにやたらテンションの高いSATOKOが乱入して3人にいじめられるという仕組み。前菜としては、もはや新鮮味に欠けるものの、安心して、いただける。
さて献立は――。駆動系別に勝ち上がってきたトップマシンが集結して、トーナメント形式で「魔王」の称号を争うという。その上、魔王経験のあるチューナーと読者からのリクエストにもとづいて特別枠を用意してくれた。が、エントリー・リストを見ると、FF車が抜けている。その内幕を土屋が素っ破抜く。
「実は出場予定のSEEKER だけどね、ここで走りこんでいたんだって。そしたら、最後にエンジンをブローさせて、来れなくなった。運がないよね」
谷口が口をはさむ。
「見上げた根性じゃないですか」
土屋「凄いよ。1日、借りきっちゃうんだから」
織戸「噂だと、かなりいいタイムを出していたそうですね」
 かくして、まず登場するのがワイルドカードとしてS2000同士が選ばれた2台である。
かくして、まず登場するのがワイルドカードとしてS2000同士が選ばれた2台である。
「魔王をとり返しに来ました」と宣言して、2年ぶりに登場したジェイズS2000。相手は群サイ常連のアルボーS2000。
ジェイズの担当ドライバー・土屋が、セッティング走行のために真っ先にコースへ飛び出した。「足回り、リヤのセッティングを大幅に変えてきました」という。入念にタイヤを温めたところで土屋が攻める。
「結構、跳ねるね」
土屋のステアリング・ワークが、いつもより頻繁で窮屈だ。おまけに路面の落葉に乗ればスリップする。だからベストラインが極端に制限されるコンディション。1本目は平凡なタイム。ピットイン。
「跳ねすぎてダメだ」
吐き捨てるように土屋がJ’sの梅本社長に告げる。前後のダンパーをソフト側に変更して2本目に入った。タイムを1秒強、縮めた。画面から聞こえる土屋の呼吸が荒い。
「怖え~。跳ねがやっぱり怖いなぁ~」
再びピットイン。跳ねを何とかしないと、最後のあたりが横に跳んじゃって、踏めない、と訴える。ギャップに対して挙動を抑えるためにリヤの車高を1ミリ、下げた。今度はどうか!?
ナレーションでレポートしてくれる。
「跳ねはあるもののコーナーを抜けるスピードは高い!」
連絡用の無線スピーカーの声がタイムを告げる。
「25″57!」
ピットで待つスタッフが「え!?」と揃って、奇声をあげた。区間レコードを叩きだしたのだ。が、そのことを土屋は知らない。冷静に連続するとコーナーと闘っていながら、まだ、迷っていた。
「ダンパーを柔らかくしたらケツが出やすくなった。さて、どっちをとるか、だな」


一方、ワイルドカードでの対戦相手、アルボーS2000を駆るのは谷口信輝だった。
全体で50キロ近い軽量化がどう影響してくるか。後半セクションでいいところが出るはずだ、という期待を背負い、「どこまで安全マージンを削るか、です。ドキドキしますね」というコメントを残してコースイン! タイムは26″860。タイヤを発熱させるために、そのまま2本目のアタック。タイムは25秒台に入れてきた。が、もう一つ、谷口は気に入らない。どうも前後の動きに一体感がないらしい。
「軽くしてしまったことによって、いままでのしっとりした落ち着きが変わって、クルマがバンバン、軽く動いてしまうので、それがうまく消せたらなぁ」
 谷口の指摘を受けて、柴田アルボー・チームはマシン調整のため、クルマをコースからひきあげる。その間も、土屋j’sは走り込みをやめない。それどころか、周回ごとにコースレコードを更新していく。一つ、一つのコーナーを抜けるリズムが軽快になっていくのが車載カメラが、正直に捉えている。
谷口の指摘を受けて、柴田アルボー・チームはマシン調整のため、クルマをコースからひきあげる。その間も、土屋j’sは走り込みをやめない。それどころか、周回ごとにコースレコードを更新していく。一つ、一つのコーナーを抜けるリズムが軽快になっていくのが車載カメラが、正直に捉えている。
マシンから降り立った土屋がグローブをとりながら、カメラに語りかける。
「いいねェ。あとは跳ねさえなくなれば、あとコンマ1秒はいけるね。安心していけるよ」
一方のアルボーはどうか? フロントのアライメント調整とリヤのキャンパー角を変更した。谷口が走り出す。1コーナーの切り増しポイントで、前後のタイヤの接地するタイミングにずれが出ると指摘されていたが、それはどうだ? 谷口のステリング操作はまだ忙しかった。ラインの乱れは払拭できないでいる。それでもタイムはJ’sに拮抗している。
 ――1時間に及ぶセッティング走行が終わって、《TOUGE BATTLE》となった。皮切りは当然ワイルドカード戦。つまりJ’s とアルボーの究極のS2000 対決である。
――1時間に及ぶセッティング走行が終わって、《TOUGE BATTLE》となった。皮切りは当然ワイルドカード戦。つまりJ’s とアルボーの究極のS2000 対決である。
ここから先は、本編でぜひ「観戦」してほしい。確かに、この「峠最強伝説 魔王決定戦」はもはや、目新しいテーマではない。が、ここまで心血を注いで仕上げてきたマシンを、土屋、織戸、谷口らが神経を削り、より走りやすくするべく走り込み、助言する。そしていよいよ勝ち抜きトーナメントが始まろうとしている。
心臓の高鳴りは、抑えようもない。で、わたしは心拍数を測ってみた。お、なんという速さだ。普段なら60前後のものが、80近くまであがっているではないか。そして、ハッと気づいたことがある。こんなときこそ、この先の峠バトルの結果予想をしたり、マシンのでき具合にケチを付けたり、それをぶつける相手が、今、この時、そばにだれもいないということだった。かつては、出来上がったばかりのベスモやホットバージョン、あるいはBMスペシャルを、スタッフと一緒に、ワイワイガヤガヤやりながら、観たものだった。
「一人はうまからず」という言葉が浮かんできた。
この言葉を遺訓としてわたしに植えつけてくれたのは、作家の藤原審爾さん(1921~1984)だった。恐らく、わが「みんカラ」友だちのほとんどは、この作家のことはご存じないにちがいないが、わたしの編集者駆け出しの時代から、生き方を指導し、温かく見守ってくれた父親代わりといってもいい、大事な存在だった。

*藤原さんのお供で丹波から城崎にクルマの旅。藤原さんは幼くして双親を失い、父の郷里岡山で祖母に育てられた。名作「秋津温泉」で若くしてデビュー、その後、1952年に「罪な女」で直木賞を受賞。代表作に「さきに愛ありて」「赤い殺意」がある。
「一人はうまからず」を、食事は一人で食べるより、だれかと一緒に食べるほうが美味しい……こう解釈しても、決して間違いではない。が、藤原さんはこう伝えてくれた。
「なぁ、正岡君よ」と前置きして、言葉を継いだ。「わたしは故あって、祖母に育てられた。祖母は格別学識のある女ではなかったが、人の道について厳しく、少年のわたしが独りたのしむことを許さず、たとえ遊び道具などでも、近所の子たちと一緒に使う野球道具のようなものであればすぐに買い与えてくれた」
あれはご一緒に丹波を旅した時の夜の宿で、だったか。
「あるときわたしは、裏山で野イチゴのみごとな群れをみつけ、それを摘み、竹籠に入れて戻り、独りで食べていたところを、祖母に見つかり、つよくとがめられたことがある。皆にわけて一緒に食べなさいというのである。わたしは山でそれを見つけ、独りで摘んだのだからといささか不満であった。その不満にこたえて、祖母は、山の幸は万民のものだと説き、一人はうまからずということばを、人としての心の持ちかたとして、私に教えた。これは世に遺った言葉ですよ、とも言った。この言葉には、この世に生きた人々の願望理想がこもっており、そういうふくらみへの感応が、時に人を動かす。強いて言えば、いまのわたしが、その一人だ」
この一節は、藤原さんがのちに新潮社から出版した『遺す言葉』の冒頭に収録されているのだが、ホットバ―ジョンを見ながら、わたしは想いだしてしまったことの意味を、もう一度、噛みしめてみよう。わかっているのは、ホットバージョンを「一人で観るのはうまからず」ということではないだろうか。
